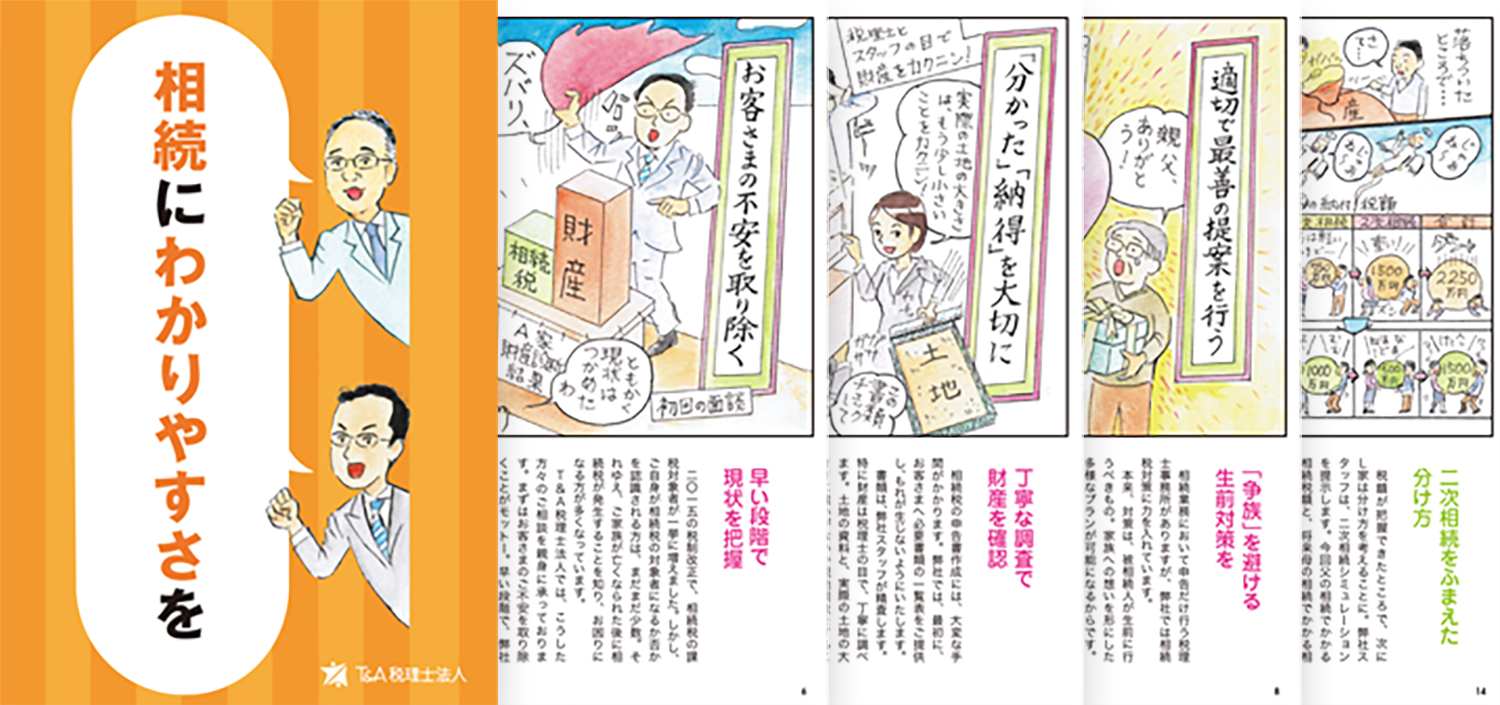HOME > TOPICS > 相続手続きに関する書類「戸籍の附票」と「住民票」って何がどう違うの?
法律に沿って申請をする書類というのは、「○○を添付して提出してください」という説明事項があったとしても、いまいち何を指しているのかがピンとこないことがありませんか?しかし、きちんと正しく進めていかないと、例えば前回触れた国税庁からの簡易な接触が入るように、手続き完了までに予定よりも時間を多く要することにもなりかねません。 今回は、いざそのときにスピーディに事を進めるためにぜひ押さえておきたい、相続手続きに必要な提出書類の「戸籍の附票&住民票」について、1つの相談ケースを用いながらその違いについて説明をしていきます。
Aさんは、母親が亡くなったことにより相続の手続きを現在進めている最中です。そのため、まずは手続きに必要な書類が何かを一つ一つ調べ始めました。そして、その際に戸籍の附票の提出が必要だと知りましたが、その内容を「住所を証明するもの」だと読み取り、「これは住民票でもよいのではないか?」という疑問を持ったのです。
つまり、必ずしも戸籍の附票という書類ではなく、より簡単に取得しやすい住民票で代用はできるものなのかということです。
しかし、そのAnswerとしては、「住民票でもオーケーとはならず、きちんと戸籍の附票を提出する必要がある」となります。
その2つは、大まかには「住所の証明」として同じことを指しているかのようにも思えるのですが、実は定義や違いがあるのです。
まずは戸籍の附票についてですが、住民基本台帳法第16条の下、現在の住所のみの情報だけでなく、その戸籍がつくられてから現在、もしくはその戸籍が除籍されるまでにわたる一切の住所が記載されているものと定義されています。 次に住民票ですが、同じく住民基本台帳法の下、第5条および第6条により、居住を記録するものという定義になります。
①まず、戸籍の附票の管理地は本籍地となり、住民票の管理地は現住所の市町村となります。
②中身については、戸籍の附票は「本籍(省略)・筆頭者(省略)・氏名・住所の変遷・住所を定めた年月日・性別」の6項目となります。
一方、住民票は「現住所・世帯主(省略)・氏名・出生年月日・性別・続柄(省略)・従前の住所・現住所の市町村の住民となった年月日・住民票コード(省略)・本籍(省略)・筆頭者(省略)・住所を定めた年月日と届出年月日・個人番号(省略)という13項目になります。
③また取得について、戸籍の附票に関しては、本人もしくは配偶者および直系血族となり、住民票については本人もしくは同世帯の人と定められています。
| 戸籍の附票 | 住民票 | |
|---|---|---|
| 管理地 | 本籍地 | 現住所の市町村 |
| 記載内容 | ① 本籍(省略) ② 筆頭者(省略) ③ 氏名 ④ 住所の変遷 ⑤ 住所を定めた年月日 (転入届を出した日) ⑥ 生年月日 ⑦ 性別 |
① 現住所 ② 世帯主(省略) ③ 氏名 ④ 出生年月日 ⑤ 性別 ⑥ 続柄(省略) ⑦ 従前の住所 ⑧ 現住所の市町村の住民となった年月日 ⑨ 住民票コード(省略) ⑩ 本籍(省略) ⑪ 筆頭者(省略) ⑫ 住所を定めた年月日と届出年月日 ⑬ 個人番号(省略) |
| 請求できる人 | 本人・配偶者・直系血族 | 本人・同世帯の人 |
現在、マイナンバーカードの普及に伴い、住民票の写しだけでなく戸籍の附票の写しもコンビニ等で交付できるようにと進められていることを総務省のホームページで紹介されていますが、後者についてはまだ対応していない市町村も多く、実際に必要となった際には、それぞれの管理地に請求することとなりますので、注意をしましょう。
今回の内容のほかにも、何か疑問点や不安な部分がありましたら、いつでも当事務所にお声がけください。1人きりで悩まずに一緒に進めていきましょう。
 0120-033-721
0120-033-721